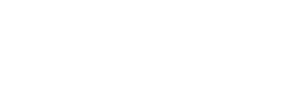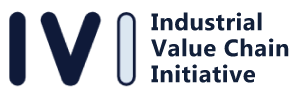日本のものづくりの構造的な転換が求められています。原材料を買って、製品に加工して、そして売るという当初はシンプルな行為で構成されていた製造業が、そのしくみが複雑さを増すにつれて、徐々に機能分化していき、ついには、モノと作りが分断されてしまったようです。単にコストと効率だけを追求する生産現場は、すこしずつ面白味に欠けたつまらないものになってしまうような気もします。非常に抽象的な言い方をすれば、モノと作りが一体となったユニットが、アメーバ―のように有機的に結合した、ダイナミックなものづくりの組織はできないでしょうか。若者から見ても、カッコいい生産現場、輝きのある生産現場であり続けるためには、“つくり”だけではなく“ものづくり”がセットになって、決して離れずにいる必要があると感じます。
そこへ至るための一つの手がかりは、最終的な製品を作るという立場と、製品を作る“しくみ”を作るという立場の使い分けです。工作機械を自分たちで作る、生産ラインのしくみを工夫するなど、からくりの世界にも通じたものづくりが、本来の生産現場にあるはずです。JSME-MSDモデルが示すような、工程設計、生産技術、生産準備といった機能を、人中心に極め、それを生産現場と一体となって進めていくということは、輝かしい現場を再構成するためのひとつの有効な手段となりそうです。
もうひとつの有効な切り口は、やはりICTによるデジタル化でしょう。ものづくりの世界は、アトムの世界であり、これに対する情報の世界は、ビットの世界と言われています。両者は、そもそもよって立つ原理、原則が異なるのです。工場で実際にモノを加工するのはアトムの世界です。工場から消費者へ製品を届ける物流の世界も、物理法則が支配するアトムの世界です。一方、情報社会におけるビットの世界は、物理法則に支配されません。情報は無限に複製でき、一瞬で空間を移動できます。ビットとアトムが融合したサイバーフィジカルな世界は、おそらく現在では想像できないことがつぎつぎと可能となるかもしれません。
ここで、議論となるのが、そうした世界を、だれが先頭をきって切り開くのか、つまり、イニシアチブを誰がとるかということです。現在のところ、ICTは欧米企業が完全に先行し、日本企業はそのキャッチアップに追われています。一方、ものづくりの世界では、日本企業に一日の長があります。つまり、ICTとものづくりの融合領域を誰が切り開くのは、日本企業である可能性も十分にあり得るのです。ビット側がアトムの世界を理解するのが早いか、それと比較して、アトム側がビットを凌駕するのが早いかです。
工場の側、つまりアトム側にとって、すでにビットの世界、つまりICTの世界は、情報システムの利活用という意味で、馴染みのある領域といえます。ただし、ICTの世界の怖さは、相手とつながってはじめて機能するという点なのです。たとえば、電話機は、通話の相手が同じプロトコルでなければ会話は成立しません。ネットワーク外部性と呼ばれる性質によって、つながる相手が増えるほど、その製品の利用価値は高まります。また、デジタルデータやプログラムなどは、複製コストが限りなくゼロに近付けられるため、製造原価と販売価格の関係を、これまでとはまったく異なる発想でとらえる必要があります。さらに、開発したICTの資産価値を維持するために、知的財産の管理が極めて重要となります。
この知的財産の管理技術は、“エコシステム”の形成と密接に関係しています。製品がそれ単独では機能し得なくなり、より大きなシステムの中のいち部品として位置付けられることが多くなっている中で、ある程度内部のしくみを公開することなしに製品は市場に普及しません。この傾向は、つながるための機能が、ハードウェアからソフトウェアに徐々にそのウェイトがシフトしていることにより、ますます顕著となっています。
製品と同様につながる工場も、他の工場とつながってはじめてパフォーマンスが最大に発揮できます。つながらなければ、工場にある高価な設備や機械は何の役にも立ちません。つながる工場をつなげている多くの部分は情報であり、広い意味でのソフトウェアなのです。サプライチェーンはもちろんのこと、設計プロセスや保全プロセスなどのエンジニアリングのチェーンにおいて、今後デジタル化がすすみ、さらにつながる工場に関する駆け引きがこれから激化していくでしょう8)。
ネットワーク外部性が支配する世界では、先行した者が莫大な利益を得ることになり、フォロワーにはもはや市場をコントロールする力は残されていません。半分アトムを引きずっているものづくりの世界では、そこまで極端ではないとしても、しかし今後、これからのICTとものづくりの融合のプロセスにおいて、フォロワーに徹した場合、非常に不利なゲームのルールで戦わざるをえないという状況となる可能性は大いにあります。
こうした状況を踏まえて、「つながる工場」研究分科会のメンバー有志は、それぞれの企業や団体における立場を超えて、まずはこうした連携のフレームワークの先鞭をつけようとしています。Industrial Value Chain Initiative(IVI)は、特に日本のものづくりを知り尽くしている精鋭たちが、これからの新たな時代に向けて、フォロワーではなく、リーダーとしてイニシアチブをとるという宣言です。
具体的にどのような課題に対して何から手をつけるべきか、また、どのような相手とアライアンスを組むかなどについて、賛同するそれぞれの企業の第一歩は、さまざまです。ただし、それぞれの企業は、これまでのように単独で課題に取り組むのではなく、複数のクラスタを形成しながら方向性を定め、同時にそれぞれのクラスタで共通となる要素技術、標準化技術を横串としてコンソーシアム全体で共有しながら進めていくことになります。そして、そうした活動を、外部に対して最大限オープンにし、海外に対しても情報を発信していくことで、逆に海外からの人材や知恵を積極的に取り込むという姿勢です。
国の政策に従ってトップダウン的に動くのではなく、かといって企業あるいは企業グループが独自に行動するのではなく、多くの日本の製造業が、和の精神でゆるやかに連携しながら、自発的に行動を起こし、同時に競争と協調の枠組みを内包しながら高め合っていくようなフレームワークがデザインできれば、それは今後、国際的にも大きな流れとなっていくでしょう。産学官がそれぞれの立場で協力し、当初から、国内と国外といった障壁をもうけず、グローバルとローカルの両にらみで進め、それぞれの活動をボーダレスに展開していくことで、日本のものづくりの国際的なプレゼンスも大いに上がると期待できます。
- 8) 西岡靖之,ボーダレス時代における「つながる工場」のための自律分散プラットフォーム,システム制御情報学会論文誌,Vol.28, No.3,システム制御情報学会(2015)